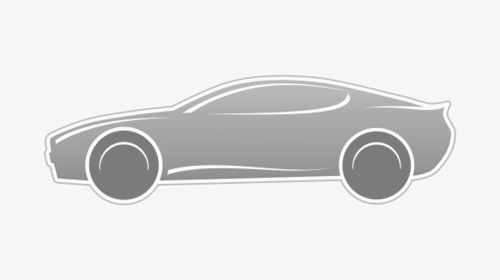【こんな人におすすめ】
●中小企業診断士の試験に合格したい人
●中小企業診断士の過去問に挑戦したい人
●中小企業診断士に興味のある人
●スキマ時間で勉強したい人
中小企業診断士(ちゅうしょうきぎょうしんだんし)とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)に基づき登録された者を指す。この省令の根拠となる中小企業支援法(昭和38年法律第147号)では「中小企業の経営診断の業務に従事する者」とされる。
「中小企業支援法」に基づく国家資格、もしくは国家登録資格である。近年は資格認定試験ではなく、登録養成機関の認定履修方式による登録資格者が増加傾向にある(登録養成機関による認定者も1次試験は通過している必要がある)。
根拠法である「中小企業支援法」には、業務独占資格(資格がなければ業務を行ってはならない)とする規定はないが、「中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令」において経営の診断又は経営に関する助言を行うものとして中小企業診断士を指定しており、政府および地方自治体が行う経営診断業務を行うものを登録する制度という位置づけになっている。また、中小企業指導法時代はあくまでも公的な診断業務を担うものという位置づけのみであったが、中小企業支援法として改正されたあとは、位置づけに変化が見られ、一定以上の能力を持つ民間コンサルタントを認定する制度という意味合いが強くなっている。
一方、法律上は名称独占資格(資格がなければ名称を使用してはならない)とする規定もないが、一般的には名称独占資格に準じる扱いを受ける場合が多い 。これは法律上の規定がなくても国家登録資格である以上、経済産業省への登録を完了すれば、中小企業診断士の資格名称が担保されることからくるものと思われる。中小企業庁のウェブサイト内でも「中小企業診断士の登録を消除されたものは同資格を名乗ったり、名刺や履歴書に記載することができなくなる」という趣旨の記述がある。
【沿革】
・1952年(昭和27年) - 通商産業省により中小企業診断員登録制度が創設される。
・1963年(昭和38年) - 中小企業指導法(現行の中小企業支援法)が制定され、国や都道府県が行う中小企業指導事業に協力する者として中小企業診断員の位置付けを法定化(第6条)。ただし、法律上はあくまでも通商産業大臣が登録を行うことのみを定めており、具体的な内容は「中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令(指導法基準省令)」(昭和38年通商産業省令第123号)第4条に、試験についてはさらに通商産業省告示で定める登録規則に根拠を置いていた。
・1969年(昭和44年) - 中小企業診断員を中小企業診断士に改称。
・1986年(昭和61年) - 従来、商業と工鉱業の二つであった登録部門に「情報」を追加。
・2000年(平成12年) - 中小企業指導法の大幅改正(このとき、表題を「中小企業支援法」に変更)により、以下のとおり大きな制度改革を実施。
・中小企業診断士の位置付けを「国や都道府県が行う中小企業指導事業に
協力する者」から「中小企業の経営診断の業務に従事する者」に変更
・登録の根拠条文の独立化(第11条)
・試験の根拠規定の創設(第12条)
・あわせて、指導法基準省令の大幅改正(現行表題は、
「中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令
(支援法基準省令)」)と、新たな試験について「中小企業診断士の
登録等及び試験に関する規則(登録等規則)」
(平成12年通商産業省令第192号)を制定。
登録部門の区分はなくなり、一本化された。
・第1次試験を選択式(マークシート)とし、第2次試験を筆記試験
(事例問題)及び口述試験として、第3次試験(実習)
を試験合格後の実務補習に移行
・2001年(平成13年) - 制度改正後初の中小企業診断士試験を実施。
・2005年(平成17年) - 新試験制度5年経過にあわせて見直しを実施するため
支援法基準省令及び登録等規則の改正が行われた。
・第1次試験に科目合格制(3年間有効)、一部科目の第2次試験への
移行及び合格基準の弾力化措置を導入
・従来中小企業大学校のみに設置されていた中小企業診断士養成課程を
民間の登録養成機関にも開放するとともに、養成課程受講資格に第1次
試験合格を必須化(いわゆる「第1次試験の共通一次化」)
・更新要件のうち実務の従事要件の強化及び登録休止・再登録制度を導入
・2006年(平成18年) - 見直し後初の中小企業診断士試験を実施。